まちづくりの仕掛け人が語る、場所に宿る意思とは -ひふみフォーラム in 十勝レポートVol.4-
Rheos Now
「ひふみフォーラム in 十勝」、3人目のゲストは、スノーピーク地方創生コンサルティング代表取締役会長・後藤健市(ごとうけんいち)さんです。
前回まで:
十勝にある「投資文化」を共有したい -ひふみフォーラム in 十勝レポートVol.1-
新たな挑戦を生み出し続ける、十勝という地域の力 -ひふみフォーラム in 十勝レポートVol.2 -
好きなことと儲かることが一体化する時代 -ひふみフォーラム in 十勝レポートVol.3 -

後藤 健市(ごとう けんいち)
1986年より郷里の帯広にて、祖父が創設した社会福祉法人に勤務するなか、地域づくりにおいて青年会議所、商工会議所青年部等に所属し、地域内外でまちづくり活動に積極的に参加。現場での経験と人脈を活かし、2001年北の屋台、2002年フィールドカフェ、同年場所文化フォーラム、2010年真冬のマンゴーづくりを手がける(株)ノラワークス、2013年プロットアジアアンドパシフィック、2017年「にっぽんのひとさら」等の立ち上げと運営に携わり、地方創生の新たなアイディアを実現するための会社や団体の設立、場所の価値を生かした企画と実践などに取り組む。現在は、これまでの地域づくりの経験とネットワークを活かし、(株)スノーピークの地方創生の担当として、国内外の地域にある自然資源や景観、環境を「野遊び」で楽しむ地域活性化の事業に取り組む。
本質的に何かを変えていくのは、小さな市民の意思
故郷である十勝・帯広に戻ってきてから32年間にわたり、地域を軸として活動を続けてきた後藤さん。その成功事例の一つに、帯広の街中にある屋台街「北の屋台」があります。
元々は車19台分の駐車場だったという小さなエリアに、20ものお店が軒を連ね店舗の入れ替わりも活発に行われています。地元の人にはそれぞれに行きつけのお店があり、狭い店内でお店の人と近い距離で、お酒と料理を楽しめる雰囲気が人気です。
今では大成功と言われる北の屋台プロジェクトも、最初は「99%失敗する」と言われていました。
後藤さん:
帯広の人はご存知だと思いますけど、絶対にうまくいかないと言われていたんです。
でもやってみないとわからないじゃないですか。今ではみんなえらそうに成功体験を語っていますけども、実際には、「やってみたら、たまたまそうだった」というだけなんですね。
最初に計画したときには、「人は賑やかな所に集まるので祭りの屋台ような場所を作ろう」というアイディアがあって、じゃあ屋台ならあまりお金をかけなくてもスタートできるということで、自分たちがやれる小さなアクションとして仕掛けたんです。
私は言葉遊びが大好きで、自分のできる範囲でアクションを起こそうとする市民のことを「志の民=志民」と呼んでいます。
私が32年間の地域の現場での活動をしてきた中で得た結論は、本質的に何かを変えようとしたときに必要なのは、大きなプロジェクトではなくて、実はそこに暮らす志民の意識を集めた、小さな活動だということです。
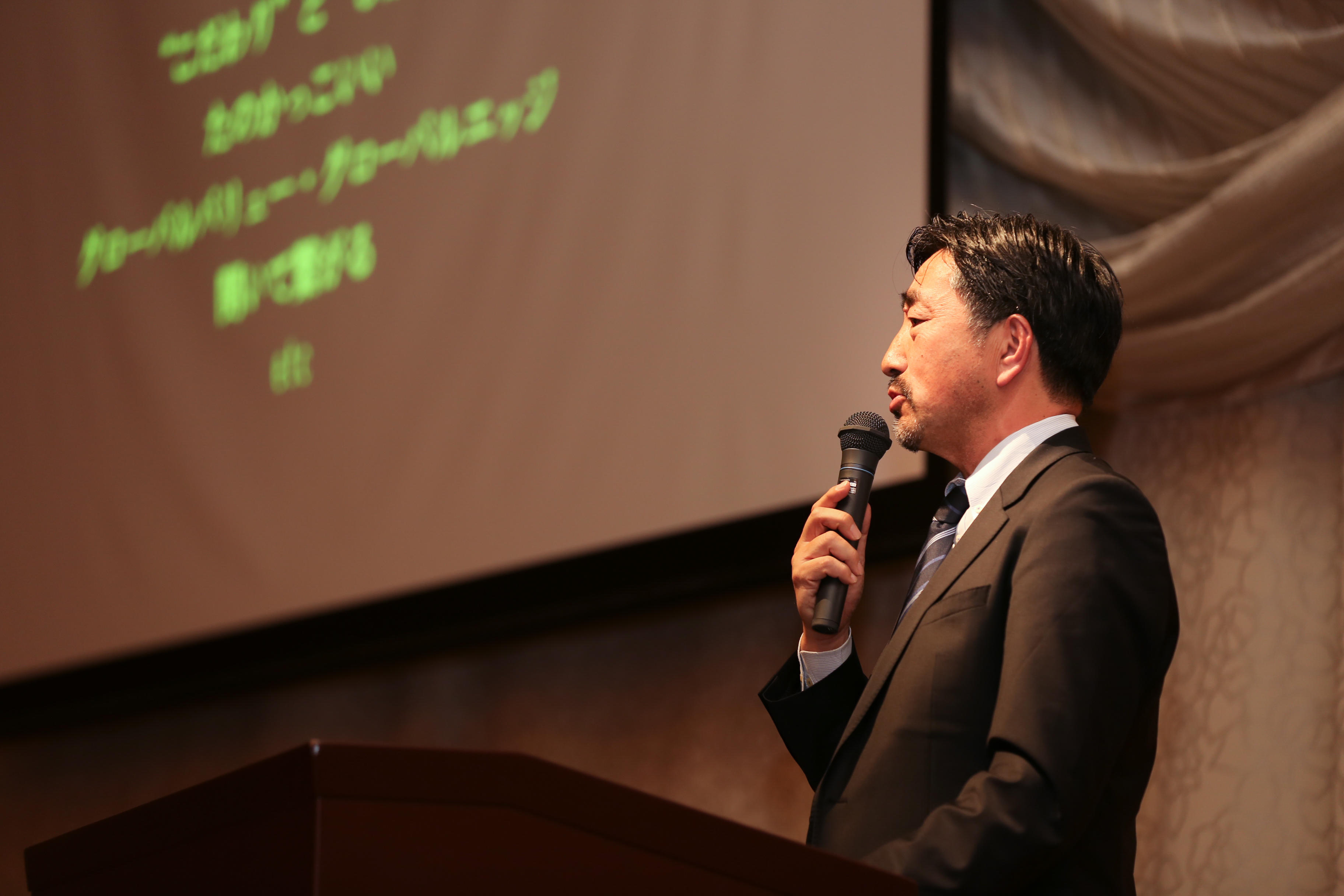
大きなことはできなくていい、小さな活動をちょっとずつやっていきながら仲間を増やす。その中にいろんな流れができてくる。
国内外の地域をフィールドとして、仲間と一緒に数多くのプロジェクトを仕掛けてきた後藤さんの言葉は、地方に暮らすフォーラムの参加者にとても大きな引っ掛かりを残してくれたように思います。
2番目に続く人の存在がイノベーションを巻き起こす
北海道は国の屯田兵によって開拓された地として知られていますが、この十勝は民間人である依田勉三さん率いる晩成社が大きな夢を描いて開拓した土地。十勝に生まれ育つ人の多くが、この歴史に感銘を受け、同時に、自分たちの祖先から受け継いでいるフロンティアスピリットを自分自身の中に感じながら育ちます。
後藤さんは、この晩成社を事例にし、イノベーションを起こすには2番目の人材が重要なのだと語りました。
後藤さん:
晩成社というとまず依田勉三さんの名前が出てきますけど、渡辺勝さんと鈴木銃太郎さんという方がおられます。
最初に来たとき、まずは北国である十勝の厳しい冬を超えなければいけなかった。鈴木銃太郎さんは、それを自ら経験するために十勝に留まっていた人で、冬を超えるには当然、原住民であるアイヌの方々にお世話にならなければいけない。鈴木さんがアイヌの方達と関係を持ち信頼をつくったからこそ、晩成社の活動が始まったんですね。
誰かが言い出したときに、その思いや夢を共有し一緒に動いてくれる人がいないと、こういう新しい活動は形にならないんです。

後藤さんが仕掛け人の一人として知られる北の屋台にも、現場で軸となって活動していたキーパーソンの存在がありました。
また、十勝の芽室町で動き始めているワインづくりも事例として登場。地元の農家のみなさんが、〝世界一のワインが作れるブドウをつくる〟という想いで、現場主導でのアクションが始まっているそうです。
後藤さん:
誰かが何かを思いつくだけでは、そのアイディアがどれだけ素晴らしくても、それだけではどうにもならないんです。それを現場でしっかりやってくれる現場力、加えてお金も含めてその活動を持続させるためのパワーが必要なんです。
それを人と人の信頼を軸にうまく組み合わせることで事業はちゃんと成長していくし、継続していく中でいろんな方の理解と関係が深まっていく。
ですから思いついた人ではなくて、その次の人、2番目の方の存在がすごく重要です。
この講演の中で後藤さんが何度も口にしていたのは、「開いてつながる」というキーワード。
閉じてしまいがちな地域の活動をオープンにして、2番目の人を含めた仲間とつながっていく。そうして動き出したアクションによって事業は成長していくのだと、強く語ります。

お金を出してでもやる楽しいことが、地域活性につながる
現在はスノーピークの地方創生部門を担当されている後藤さん。〝「楽しい」と「美味しい」で場所と人、人と人をつなぐ〟活動を、スノーピークの野遊び展開の中で仕掛けています。
地元の人が認識していない素晴らしい素材が十勝にはあり、マイナスイメージに捉えられがちな冬も、仕掛け方によってはいくらでも遊ぶことができるのだと言います。
後藤さん:
我々にとって当たり前のものを、地域住民がもう一度ちゃんと認識し磨きをかけること。それができないとどうしても大きなハード、施設などに依存してしまいます。そういうものも必要ですけど、それぞれの地域にある当たり前の自然と都市の文明的機能とのバランスこそが地域にとって大事です。
都市と田舎はどちらかで語られがちですが、僕は「どっちも」の時代だと言っています。どっちも重要なんですね。
後藤さん:
地域の現場で、地方創生の活動をして思うのは、まじめなのはいいけど、まじめすぎてしまうんですよね。それで、やっていることがつまらなくなるんですよ。
やっていることが楽しくなくなると何が起きるかというと、お金もらえるからやるという意識になってしまう。だから、自らお金だしてまではやろうということにはなない。
さっきの山井の釣りの話もそうですが、楽しいことは、自分のお金と時間を使ってわざわざ行くじゃないですか。好きなこと、面白いことには思いっきりお金を使い、そうじゃないことにはすごくシビアになる。
そうだとしたら、地域づくりや地方創生もも、っと楽しい、ワクワクすることを仕掛けていくと、今とは違う状況で日本の地域を活性化できるはずです。

場所に意思がある
場所文化プロデューサーとして活動する後藤さん。〝場所文化〟という言葉を使うことになったのは、ある先生から教わった〝場所の意思〟の話がきっかけでした。
場所に実は意思があると言うことを、十勝に戻ってきた若い頃に教えていただいたんですね。地域でいろいろなことをやっていましたが、それは私たちが何かをやっているのではなくて、場所の意思の元で活動させていただいているんだと教わったんです。
様々な地域で活動をする後藤さんは、その言葉を今でも大切にしていて、場所の意思を感じながら仲間と一緒に活動しているのだそう。
レオスやこれまでのスピーカーのみなさんを含め、行動を起こす人が集まる十勝という場所の力。その源は、開拓の時代から受け継がれてきた十勝という場所の意思があるのだと後藤さんは感じています。
後藤さん:
依田勉三さんは50年経って、けっきょく会社を失ってしまうんです。
ですが、今の十勝・帯広の姿が、依田勉三さんたちが思い描いた姿だとしたら、150年以上もの間、誰かが未来の姿を夢見て行動する役割を担う必要があることを、この場所に住む私たちたちは、地域の歴史や、地域と自分たちのDNAから学んでいる。
ですから大切なのは結果ではなくて、実はチャレンジしていくことそれ自体に価値があります。たとえ失敗しても、あとに続く人たちが先人の背中を見て、それを追いながら結果を出していく。
それが、開拓時代の先人たちから受け継がれている、この十勝という場所の意思だと思っています。
ひふみフォーラムレポート・Vol.5に続く
取材・文:神宮司 亜沙美
北海道大樹町出身、在住。大樹町地域おこし協力隊を経て独立。北海道の作り手の物語を届けるオンラインショップ「北海道ローカルマーケット」を運営する他、ストーリーの届け手として企業の情報発信をサポートしている。
写真:澤田 希望

[an error occurred while processing this directive]
