青森のねぶたに学ぶ チームのものづくり -全国ありがとうキャラバン開催レポート-
ありがとうキャラバン
6月9日(土)、青森県青森市にて「全国ありがとうキャラバン@青森」を開催しました。
岩手県に続き、五十嵐(社長室)と石川(ダイレクト営業部)、松永(マーケティング・広報部)、田中(経理財務部)でやってまいりました。
今回のレポーターは田中が務めます。
田中 麻里奈(たなか まりな)
2016年10月入社。経理財務部にて日々の支払い対応や月次決算の取りまとめ、年次決算業務を行なっています。
経理の仕事は常に正確さを求められますが、経験や専門知識を習得して、各部署から相談があったときに、決められた方法を伝達するだけでなく、新しい提案やよりよいアドバイスができるようになることを目標としています。

帆立貝釣りに初挑戦!
青森駅に到着してまず向かったのは、「帆立小屋」。こちらで、帆立貝釣りに初挑戦しました。
りんごやお米、新鮮な魚介類など、青森には日本を代表する食材が豊富にありますが、なかでも帆立貝の生産量は北海道に次いで全国2位。
さらに、6月は生産量が多い上、グリコーゲンを多く含むためもっともおいしい時期とされているそうです。(「青森県ほたて流通振興協会」より)
帆立貝釣りのコツは“口をあけた貝のヒモに釣り針をかける”こと、さっそく挑戦しました。

4人合わせて、釣果は19枚!
半分ずつ、貝蒸しとお刺身にしてもらいました。さばきたての帆立貝は肉厚でむちむち、甘くておいしかったです。


“白い”ねぶた……!?
新鮮な帆立貝をたっぷりと堪能したあとは、ねぶた小屋に移動しました。
なんと、今回、8月の祭り本番にむけて制作真っ只中のねぶたを特別に見学させていただきました。

ねぶたはこの中に!
(ねぶたは製作中のため、写真ではお見せすることができないのですが、すごい迫力でした!)


(白いねぶたは骨組みに紙がはられた墨入れ前の状態です)
これまでにいくつものねぶたを制作してきた竹浪先生にお話を伺いながら、骨組み、電気配線、紙はりの様子を見学させていただきました。
ねぶたは秋の収穫祈念し灯籠流しをしていたことが起源だそうです。その昔、江戸時代ではそれぞれの家で行われていた身近な民俗行事だったとのこと。
“和紙を使うこと”と“人型の灯籠であること”という原則はそのままに、ろうそくがLED電球になったりと、加工しやすい素材がみつかれば採用し、少しずつ変化をとげ続けています。
「同じねぶたは二度とない。毎年違ったねぶたに出会えることが人々を魅了する理由なんでしょうね」と竹浪先生。
ねぶたの制作は、1枚の下絵から始まるそうです。構想を練り鉛筆で下書きをして色をつけ、下絵ができあがります。
そして、驚くことに、ねぶたには設計図がないそうです。ひとつのねぶたにかかる何十人ものチームメンバーが下絵からねぶたのイメージを共有し、それぞれの役割を担い、繋ぎ、ひとつのねぶたが完成します。
みんなの手でひとつのものをつくりあげていく。ものづくりだけでなく、人と人との関係や組織においても共通したものがあると思います。
レオスの一員になってまもなく2年になりますが、ひふみという商品がたくさんのお客様のもとで愛され続けられるよう、これからもつくりあげていく、そんな喜びを分かち合う仲間に出会えたことにうれしく思います。

そしてセミナーへ……!
資料にメモをびっしりと書き込んでくださるお客様や、時折うんうんとうなずきながら耳を傾けてくださるお客様を何人もお見かけしました。


また、今回、青森銀行の行員の皆様も多数ご参加くださりました。普段のお客様と接するときの様子や最近のレオスに対するお声を教えていただいたりと、熱心な皆様に支えられていることを知り、改めて感謝申し上げます。
最後にセミナーにご参加くださった青森の皆様、ねぶたの取材にご協力くださった竹浪先生、貴重なご縁を結んでくださった青森銀行の白川さん、ありがとうございました。


(レポーター:経理財務部 田中 麻里奈)
皆様にお会いできるのを楽しみにいたしております!
山梨(甲府市):7月6日(金)19:00~
静岡(浜松市):7月7日(土)13:30~
宮城(仙台市):8月3日(金) 18:30~
秋田(秋田市):8月4日(土)14:30~
福島(福島市):8月24日(金) 18:30~
山形(山形市):8月25日(土) 14:30~
石川(金沢市):9月7日(金)18:30~
福井(福井市):9月8日(土)14:30~
沖縄(那覇市):9月21日(金)18:30~
福岡(福岡市):9月22日(土)10:00~
福岡(福岡市):9月22日(土)13:30~
鳥取(鳥取市):10月5日(金)18:30~
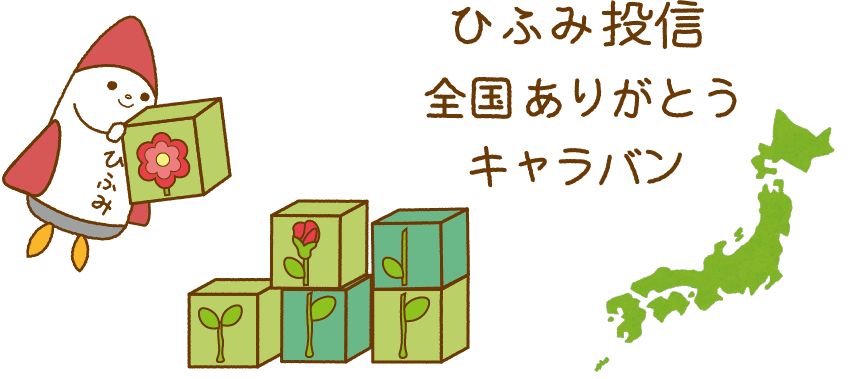
[an error occurred while processing this directive]
